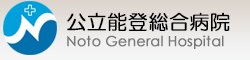ごあいさつ
|
基本理念・基本方針
|
|
施設概要
|
臨床倫理
|
|
病院沿革
|
組織概要
|
|
経営状況
| 病院指標
|
|
広報
|
厚労大臣の定める掲示事項
|
|